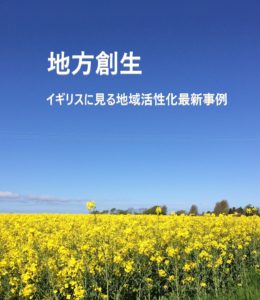あなたは車を運転しますか?そして、ナビゲーションアプリを使っていますか?
静かな住宅街に忍び寄る“最短ルート”の弊害
ロンドン住まいの今は公共交通を利用することが多いわたしですが、イギリスの地方に住んでいた時は、毎日のように車に乗っていました。
昔は、知らない場所に車で行くのが苦手でした。特に1人で運転していると、地図を開くこともままならず、不安や手間がつきものだったものです。でも、今はナビがあります。「Googleマップやカーナビの案内に従いさえすれば、目的地まで迷うことなくたどり着ける。」そう思って、私はその便利さをありがたく享受していました。
ある日、行ったことのない目的地に1人で運転して向かっていた時です。幹線道路が渋滞していたようで、Googleマップのナビは私を住宅街の裏道へと案内しました。「こんな道、通れるの?」と思うような細い道。しかもスピードバンプ(減速帯)が連続していて、快適とは言えません。でも確かに、渋滞は避けられています。
でも、運転しながら、思いました。
「この道、本来は地域住民のための生活道路だったはず。
少し前にナビがなかった頃には、外部の車がここを通ることはほとんどなかったのではないか?」
そこに住む人たちは、静かだった住宅街を通り抜けする車に乱されて、不満を感じているのではないでしょうか。
それから別の日に車をサービスに出したところ、サスペンションに問題があると言われました。普段は車をあまり使わないのでどうしてだろうと思ったら、整備士に「スピードバンプのせいでしょう。最近どの車もそうなんです。」と言われました。ナビゲーションアプリによる「抜け道」案内の結果、スピードバンプを頻繁に通過する車が増えたことで、サスペンションへの負担やトラブルが増加しているそうです。
このような「ナビによる通過交通の流入」は、今や世界中の住宅街で問題になっています。
静かな生活道路を襲う“抜け道”化の波
急増する通過車両と渋滞
ナビアプリは、幹線道路が混雑していると、最短ルートとして生活道路を選ぶことがあります。かつては地元の人しか通らなかった道が、今では通勤者や観光客の“裏ルート”となり、住宅街に渋滞が発生するようになっています。
安全性・環境への深刻な影響
住宅街に交通量が増えることで、歩行者(特に子供や高齢者)の安全が脅かされます。騒音や排ガスなどの環境悪化も見逃せません。イギリスの研究では、生活道路では幹線道路よりも事故発生率が高いというデータもあります。
大型車両が狭い道に侵入
一部のナビは車両のサイズを考慮しないため、トラックや観光バスが生活道路に進入。すれ違いや事故、インフラの損傷といった問題も引き起こしています。
住民の生活リズムへの影響
クラクション音、渋滞の列、夜間のエンジン音。本来静かなはずの生活空間が騒々しくなり、睡眠障害やストレスを訴える住民も増えているそうです。
車への負担や損傷
スピードバンプなどを頻繁に通過すると、車のサスペンションには大きなストレスがかかり、損傷や寿命低下の原因になることが指摘されています。特に、ナビに従って普段使わない道を通るドライバーや、生活道路を多用する流入車両が増えた結果、以前よりもバンプを通過する回数や速度、負荷が増しているケースが多いということは現場の自動車整備士などでも話題になっています。
なぜこんなことが起きているのか?
ナビゲーションアプリは「最短」「最速」を最優先するため、住宅街であっても少しでも時間短縮につながるならルートに組み込まれてしまいます。その結果、本来は外部交通を想定していない生活道路に車両が集中し、さまざまな弊害が生まれているのです。
対策の現状と可能性
各国での取り組み
各国では、生活道路への通過交通を抑制するため、さまざまな対策が講じられています。
たとえば、進入禁止の設定や一方通行化、スピードバンプ(減速帯)の設置など、物理的に交通の流入やスピードを制限する方法がよく用いられています。
また、Googleマップなどのナビゲーションサービス提供者に対し、「この道をルート案内から除外してほしい」といった申請を行う自治体や住民も増えており、プラットフォーム側との調整も模索されています。
さらに、「ナビを切ってください」などの注意喚起を促す標識の追加によって、ドライバーの意識に働きかける試みも行われています。
オランダの小さな町のゲリラ対応
オランダの海辺の町ザンドフォールト(Zandvoort)の住宅街に住む住民は、過度な交通混雑や違法駐車に困り果て、ゲリラ的な行動に出ました。Googleマップ上で自分たちの通りを「通行止め」と虚偽報告し、ナビゲーションアプリを“騙す”ことに成功したのです。これにより、実際には通行可能にもかかわらず、カーナビが該当地域を避けて案内するようになり、一時的に交通量が減少しました。
とはいえ、この結果として、迂回した車両がほかのエリアで新たな渋滞やトラブルを引き起こしているとがわかりました。これに対し、自治体は正式な対応として、主要な道路入口に「ナビゲーションをオフにし、指定されたルートに従ってください。」という標識を設置することに。
この一連の騒動は、「ナビアプリによる経路集中」や「デジタル情報の信頼性」、そして「住民発のデジタル抗議行動」という現代的な都市問題を象徴しているといえます。
日本でも広がる問題と対策
日本でも同様に、幹線道路の渋滞時、ナビ案内を頼りに「抜け道」となる生活道路に通過交通が集中するケースがあります。
たとえば、主要な渋滞ポイントが連続する杉並区高井戸付近で環状8号線の抜け道となっている生活道路では、交通事故発生率が東京都の市区町村道の平均の約5倍も高くなっていることが報告されています。本来なら環状8号線を通行すべき車両が、渋滞を避けようとして、安全で快適なコミュニティ空間であるべき生活道路に流れ込んでいることが大きな原因と考えられているのです。
日本では、以下のような対応が取られ始めています。
- 「ゾーン30」などの速度制限・進入規制の導入
- 国土交通省によるビッグデータ分析と事故防止策
- 観光地・イベント時の迂回案内の強化
結論:ナビの時代に“地域の声”を反映させるには
ナビゲーションアプリは私たちの移動を効率化してくれますが、その設計が地域の生活や安全を脅かしてしまうこともあります。技術や便利さだけに任せるだけでいいのかという事を、ナビゲーションアプリ提供者や交通政策担当行政、地方自治体などが議論する必要があるでしょう。
「どの道を通るか」ではなく、「誰の暮らしの中を通っているのか」
という視点がナビにも、ドライバーにも求められる時代と言えます。